
オムロンで画像処理・機械学習を専門とし、これまで顔画像処理や生産ラインにおける画像センシングアルゴリズム開発に従事してきた井尻 善久・博士(情報科学)。
近年は「誰でも、どこでも、何でもつくれるモノづくり」を実現するため、誰もが簡単に使えるロボットの開発にチャレンジし続けている。
なぜ誰もが簡単に使えるロボットが必要なのか?モノづくりの現場で求められる「気が利く」ロボットとは何なのか?そういう考えを持つに至った原体験とは?
彼のチャレンジに迫った。
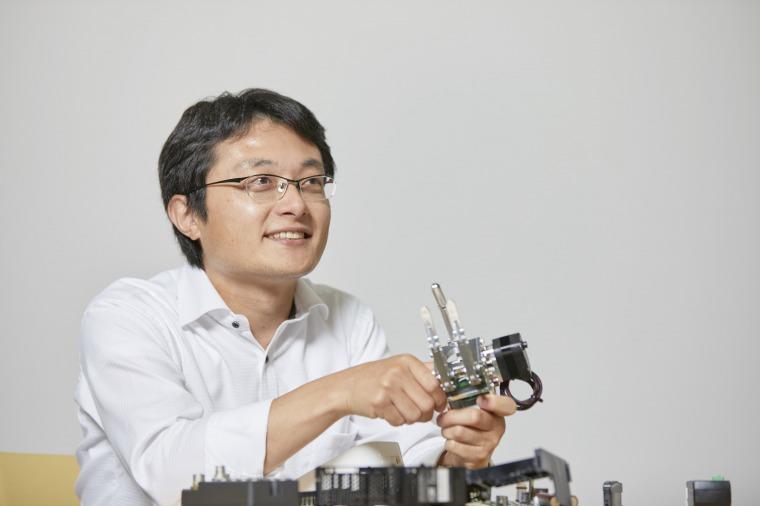
消費者ニーズの多様化に伴い、つくる製品のバリエーションの増加など、さらなる柔軟性が求められている現代のモノづくり。
人手不足の影響から、ロボットに対する期待は大きい。
一方、既存のロボットは「必ずしも現場で使いやすい状況ではないのではないか」と井尻は指摘する。
「ロボットに正確な動作をさせるためにはロボットハンドやロボットが掴んだものを置く場所などを掴む対象や作業に応じて一つ一つ設計する必要があります。
それでは結局、高機能なロボットが限られたことしかできない機械になってしてしまい、つくる製品の品種をどんどん増やしていくような柔軟なモノづくりは困難です。
このため、製造業は熟練者に頼ってきたわけですが、少子高齢化による労働者人口の減少により、行き詰りつつあります。
仮にロボット化できる作業であったとしても、ロボットを安全に扱うには、講習を受け、実際に動かす経験を積まなければならず、ロボットのプログラミングには素人を受け付けない敷居が存在します。
現場での設定にも膨大な時間がかかり、一つ間違えばペナルティも大きく、下手に扱うことができません」。
人手不足解消のためのロボットのはずなのに、結局はエキスパートが必要という状況を生み出している。
ロボット操作をシンプルにすることが必要だ。井尻はそう考えた。
「ロボットが現場で必要とされる一通りの動作を実行するスキルを覚えておき、それらを人が必要な順序で組み合わせる、そしてロボットは現場で起こる変化に合わせながらタスクを実行できるようになれば、"What(何をすべきか)"のみを教示すればいいわけです。
"How(どのように実現するか)"の教示は飛躍的に減り、エキスパートでなくてもロボットを使えるようになります。これにより、ロボットを扱うのは飛躍的に楽になると考えています」。

「人は転びそうになったら、反射的に立て直そうとしますよね。
モノを掴む時も対象物との距離感や形状を瞬時に認識して確実につかみ、落としかけても反射的につかみなおす。失敗することはほとんどない。
私が目指すのは、そうしたメカニズムをロボットで実現することです」。
一方、モノづくり現場では、人が手を入れられない自動化は好まれないという。
「モノづくり現場では、どんなにしっかり検証して生産ラインをつくったとしてもトラブルが起こることはあります。
生産を止めないのは最も大事ですが、少し止まってもすぐに調整し生産に復帰できることが重要です。
だから小難しいシステムより、わかりやすいシステムが好まれます。これが、モノづくり現場で得体の知れないAIが嫌われる理由です。
ですから現場でAIの良さを引き出そうとすると、人の注文に合わせて挙動を改善できる"気が利く"ロボットが重要になると考えています。
スピード重視なのか精度重視なのか?どこを持てばよいのか?どこを持ってはいけないのか?現場では、生産工程によってさまざまな制約やそれに合わせた調整が必要になります。
AIが良かれと思って考えたことが、その工程ではよくないこともよくある。
つまり、一般的な意味で賢いだけのAIでは使い物にならないわけです。人の求めに応じ柔軟に挙動を改善できる賢さを持たなければなりません。
しかし、昔のように一挙一動をプログラミングするのではなく、人の最小限の注文で実現できなければならず、そこには"常識"が求められます。
このように、成長し続けるAIをつくりたいと考えています。
人は、周囲から、もっと速く!とか、もっと丁寧に!などと言われただけで、動作改善ができます。
これは人にとっては自然なことですが、現状の"固い"AIにとっては困難なことなんです」。
人の注文に応じて、"気が利いた"行動を実現するAIこそが鍵となる。
モノづくりの現場や状況、ユーザの求めに応じて、機転を利かし、望みどおりに簡単に動かせる、"気が利く"AIを搭載したロボットだ。
"学習済み"AIは、学習された条件下では高精度だが、学習データと異なる環境下において何が起こるかわからず、挙動の改善も難しい。
これに対して"成長し続ける"柔らかいAIがこれから重要になる。
その実現に向け、井尻たちのチームは、ロボットにおける様々な動作の基本となる、より自然かつ柔軟な「モノをつかむ」動作から技術を積み上げていっているという。
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
今までにないまったく新しいチャレンジは、研究室を飛び出してモノづくりの現場に向き合うことで生まれてきたと井尻は言う。
現在、知能システム研究開発センターに所属する井尻だが、事業部で製品開発に留まらず営業サポート、顧客サポートなど、幅広い業務を通じて修行を積んできた。
「そのなかでも、顧客サポートを通じて出会った、社内外におけるモノづくり現場の真剣な技術者たちの姿は本当に刺激的でした。
ひとたび問題が生じれば、直すまで帰らない気力、直すまで帰さない拘り、現場で直してくる技術力、こうした一歩も妥協しない厳しさと技術力の戦いが繰り広げられています。
そうした活動の積み重ねが、真似のできない高い品質を生み出す。
しかし一方で、モノづくりに関わる技術者達は高まる品質要求に翻弄され、過酷な作業と長時間労働を強いられ、頑張りすぎるほど頑張っているようにも見えました。
その姿を見たときに、もっといろんなことをシンプルに、簡単にすれば、技術者の役に立てるのではないかと考えるようになりました」。
機械が現場環境・ユーザに合わせてもっと自律的に考えるようになれば、もっとシンプルになるはず。
そして、機械にできることは機械がやり、機械が出来ないことを人がする現場に変えていきたい。
そんな井尻の信念が、"気の利くロボット"の開発という新たなチャレンジを支えている。